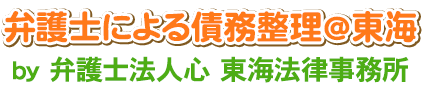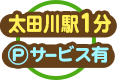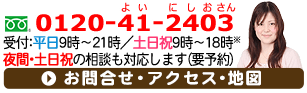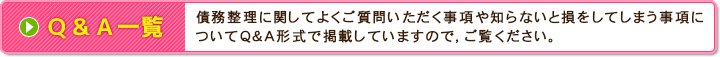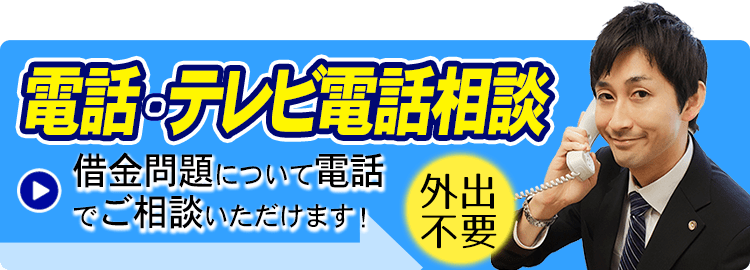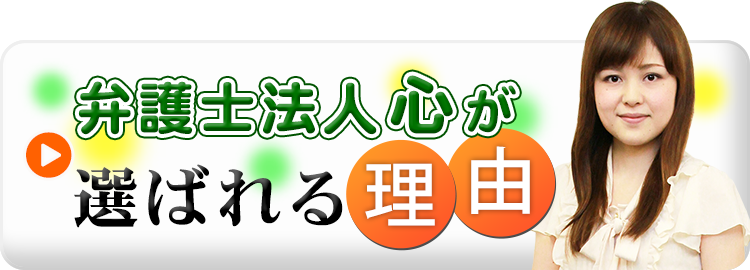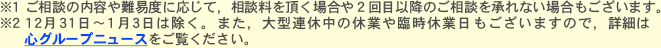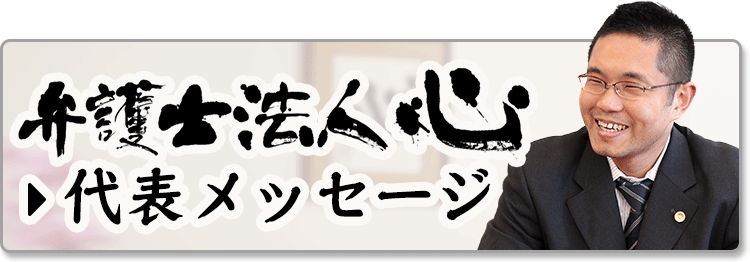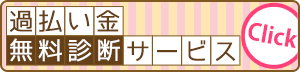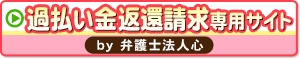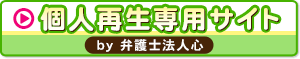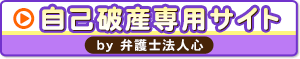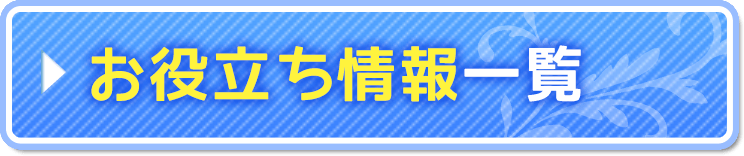「過払い金」に関するお役立ち情報
過払い金の請求にはどのような資料が必要か
1 過払い金の請求の概要
過払い金は、簡単にいうと、貸金業者に対して「過」剰に支「払」ったお「金」のことです。
利息制限法1条1項によれば、金銭消費貸借について、元本額が10万円未満の場合は年20%、元本額が10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本額が100万円以上の場合は年15%を上限とし、その超過部分は無効とすると規定されています。
貸金業者が、上記の利息制限法で定められた上限を超える利率を設定して、利用者がその利率で返済していた場合、利息制限法で定められた利率で利息・元本へ充当すると、本来支払う義務のない分まで貸金業者へ支払っていたことになります。
このような過剰な支払いを貸金業者に返還請求するのが「過払い金返還請求」の手続きです。
以前は多くの貸金業者が、利息制限法を超える利率の設定をしていました。
超過利息でも、利用者が任意に支払った場合は有効な返済とみなされるというのがその根拠です(※旧貸金業法43条1項に基づく「みなし弁済」といわれます。)。
しかし、平成18年1月13日の最高裁での判決以降、みなし弁済が認められる条件が厳格化されてからは、ほぼすべての貸金業者は、超過利息の設定を撤廃しました。
2 過払い金の請求を行うために必要な資料
過払い金の存在およびその額を確認するためには、貸金業者との当初からの全取引を確認する必要があります。
過去の取引の内容は、貸金業者に「取引履歴」の開示を請求することで確認することができます。開示された取引履歴をもとに、利息制限法で定められた上限利率に基づいた返済を行っていた場合の返済額等を計算しなおし、過払い金の有無や額を算出します。
「貸金業者が取引履歴の開示を拒んだらどうなるのか」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、貸金業法では、債務者の貸金業者に対する取引履歴、つまり帳簿の閲覧請求権を認めており、債務者から取引履歴の開示請求がありますと、貸金業者は基本的に応じなければなりません。
貸金業者ごとに開示までのスピードに差異はあるものの、開示に応じない貸金業者は皆無に近いように思われます。
また、取引履歴がなければ、過払い金請求の相談ができないというわけではありません。
借入れをしていた時期・期間についての情報があれば、過払い金が生じるかどうかの大まかな判断は可能です。
検討の結果、過払い金が生じる見込みがあると判断された場合には、委任契約後に代理人となった弁護士が貸金業者へ開示請求をすることも多くあります。
資料収集についてのご不安を抱えていらっしゃる方も、まずはお気軽に当法人の弁護士へご相談ください。